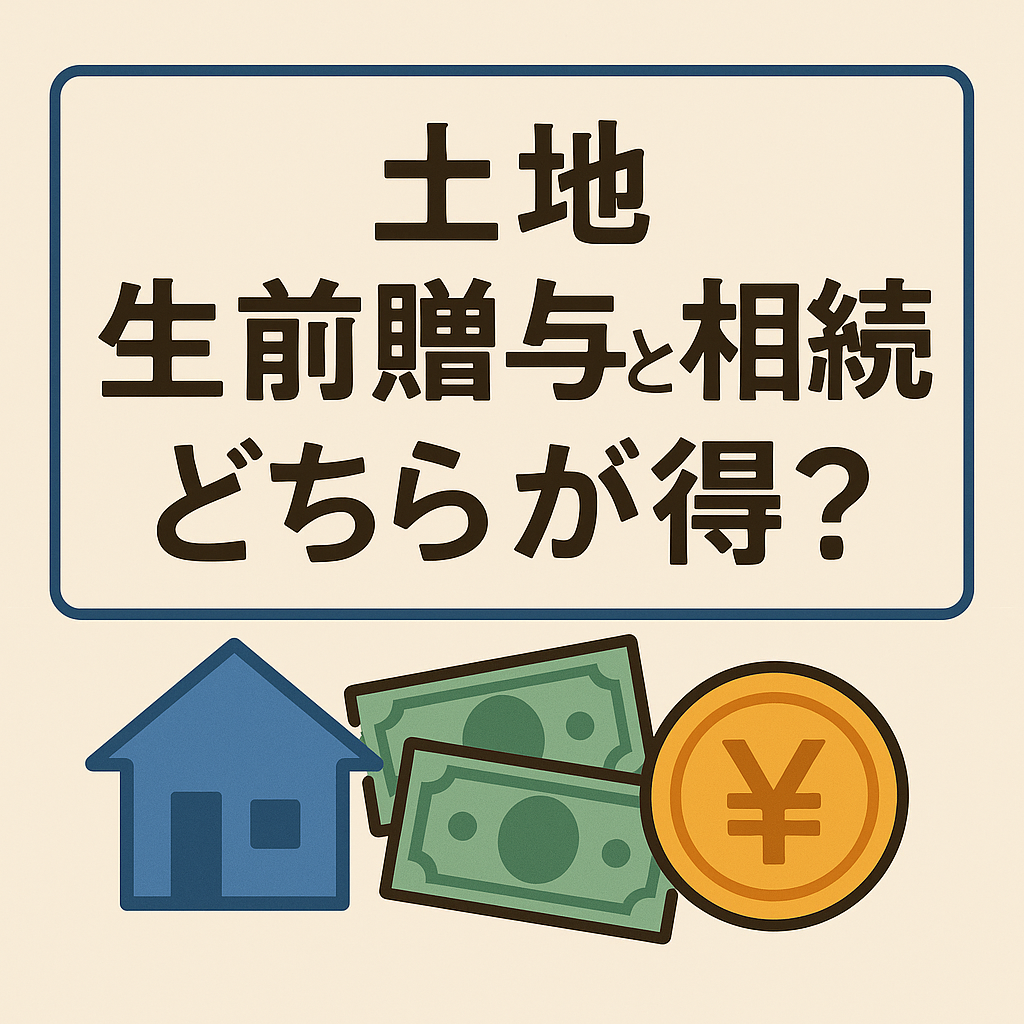まずは結論だけ知りたい人へ(60秒まとめ)
課税の基本線
・相続は「3,000万円+600万円×法定相続人」の基礎控除内なら相続税は0円。この枠に収まる方は、原則として相続のほうが有利になりやすい(国税庁)。
・自宅敷地は「小規模宅地等の特例」で330㎡まで評価80%減が可能(贈与では不可)。自宅の承継は相続側が有利に傾きやすい(国税庁)。
贈与(生前)を選ぶ典型例
・将来の地価上昇が見込まれる遊休地・投資用地など、相続の特例メリットが薄い土地。
・相続トラブル(共有・遺産分割)を回避したい、認知症リスクの前に名義整理をしておきたい。
・相続時精算課税(2,500万円+年110万円)を利用し、贈与時の負担を抑えつつ早期承継・早期活用を図りたい(最終的に相続で清算/国税庁)。
2024年以降の新ルール(重要)
・暦年贈与は相続時に原則7年分を加算(段階的に拡大)。
・4〜7年前分の贈与は「各年ではなく合計から100万円を控除した残額」を加算。各年110万円以下でも、4〜7年分の合計が100万円を超えれば加算対象になり得る(国税庁)。
登記・取得時の諸税(ここで差が出る)
・贈与で名義変更:登録免許税2.0%(固定資産税評価額ベース)/不動産取得税は課税。住宅・宅地は特例で原則3%、宅地は課税標準1/2(現行は令和9年3月31日までの軽減が目安)。
・相続で名義変更:登録免許税0.4%/不動産取得税は非課税。諸税トータルは相続が軽くなりがち(国税庁・茨城県税)。
期限(遅れると不利)
・贈与税申告:翌年2/1〜3/15(国税庁)。
・相続税申告:相続開始を知った日の翌日から10か月以内(国税庁)。
・相続登記:相続で取得したことを知った日から3年以内に申請義務(2024年4月施行/法務省)。施行日前の相続にも経過措置あり。
迷ったら「相続有利かの検証 → 贈与の狙い撃ち(地価・トラブル・資金需要)」の順。取手市・利根町の地価感、売却実務は取手戸頭店が数字で具体化します。
目次
・土地の生前贈与と相続、どちらが得なのか?(基本の違いと考え方)
・それぞれのメリット・デメリット(比較表つき)
・税金の負担を比較する(贈与税・相続税・諸税)
・税金のシミュレーション:具体例で見る(2ケース)
・生前贈与が有利なケース(トラブル回避・早期活用・地価上昇)
・相続が有利なケース(基礎控除内・小規模宅地等の特例)
・手続きの簡便さを比較する(贈与・相続の実務フロー)
・生前贈与と相続の注意点(契約書・7年加算・遺留分ほか)
・専門家に相談するメリット(税理士・司法書士の役割)
・まとめ:どちらが得かはケースバイケース
・FAQ(よくある質問)
土地の生前贈与と相続、どちらが得なのか?(基本の違いと考え方)
生前贈与は、贈与者が生存中に無償で財産を渡すこと。受贈者は原則として贈与税の対象で、土地・建物では登録免許税(2.0%)や不動産取得税も発生します(住宅・宅地は特例で原則3%、宅地は課税標準1/2の軽減・期限あり)。「毎年110万円までの暦年贈与」や「相続時精算課税(2,500万円+年110万円)」など制度を組み合わせた計画的承継が可能ですが、2024年以降は7年加算により、従来ほどの暦年贈与メリットが出ない場面も増えます。さらに、贈与は贈与契約書の作成・登記・申告まで自分たちで完結させる必要があるため、認知症リスクによる意思能力低下の前にスケジュール設計をしておくのが肝要です。
相続は、被相続人の死亡により財産が包括的に承継されること。最初に基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)を差し引き、課税判定を行います。居住用宅地については小規模宅地等の特例(330㎡まで評価80%減)など相続固有の強い特例が使えるため、自宅の承継は相続が有利になりやすいのが実務感覚です。諸税面でも、相続登記の登録免許税は0.4%で不動産取得税は非課税。2024年4月から相続登記は3年以内に申請義務化され、放置によるリスクも明確化しました。総じて、自宅・実家といった居住用資産は相続寄り、遊休地・投資用地など特例メリットが薄い資産は贈与の検討余地、というのが判断の出発点になります。
それぞれのメリット・デメリット(比較表つき)
生前贈与のメリット
・早期承継・早期活用:受贈者名義で売却・賃貸・担保化をすぐに実行可能。住宅取得等資金の非課税特例(省エネ等1,000万円/一般500万円)を活用できる(贈与年の期限あり)。
・トラブル抑止:受け手や持分を生前に明確化でき、共有や揉め事の芽を減らせる。
・評価の固定:地価上昇前の評価で移転できる(相続時精算課税は相続時に清算)。
生前贈与のデメリット
・贈与税は相続税より税率構造が重めで、高額一括移転は負担が大きくなりがち。
・2024年以降の7年加算で暦年贈与の節税効果が目減り。
・贈与登記2.0%・不動産取得税(住宅・宅地3%/宅地は課税標準1/2)など、諸税の初期コストが相続より高い。
相続のメリット
・基礎控除+小規模宅地等の特例など、相続にだけある強力な評価減が使える。
・相続登記0.4%/不動産取得税非課税で、名義変更コストが低い。
・遺言/遺産分割で配分の自由度がある(法定相続分・遺留分に注意)。
相続のデメリット
・評価・申告・協議など手続きは複雑。
・相続税は10か月以内に現金納付が基本。手元資金が薄いと売却・借入の検討が必要。
| 観点 | 生前贈与 | 相続 |
|---|---|---|
| 税の基本 | 贈与税(110万円超は累進)/登記2.0%/不動産取得税(住宅・宅地3%・宅地1/2) | 相続税(基礎控除・特例)/登記0.4%/不動産取得税は非課税 |
| 主な特例 | 相続時精算課税(2,500万円+年110万円)/住宅取得等資金非課税 | 小規模宅地等(居住330㎡80%減)ほか |
| 節税の鍵 | タイミング(地価・7年加算)×制度選択 | 基礎控除内か/特例の適用可否 |
| 手続き | 贈与契約→登記→贈与税申告 | 遺言確認→分割協議→登記→相続税申告 |
| 影響 | 早期活用・トラブル抑止 | コスト低め・特例が強力 |
※不動産取得税の標準税率は4%ですが、住宅・宅地には特例で3%が適用され、宅地は課税標準1/2の軽減が設けられています(現行は令和9年3月31日までが目安/適用要件に注意)。
税金の負担を比較する(贈与税・相続税・諸税の基礎)
贈与税(暦年課税):受贈者ごとに年間110万円まで非課税。超過分は累進税率。直系尊属→18歳以上への贈与は「特例税率」で計算し、一般税率よりやや緩やかです。
相続時精算課税:通算2,500万円まで贈与時課税なし+2024年分以降は年110万円の基礎控除が使えます。最終的に相続時に合算清算されるため、地価見通しや納税資金計画をセットで検討します。
登録免許税:贈与は2.0%、相続は0.4%(課税標準は固定資産税評価額)。
不動産取得税(県税):贈与は課税(住宅・宅地は特例で3%、宅地は課税標準1/2の軽減。現行は令和9年3月31日までが目安)。相続は非課税。
期限:贈与税申告は翌年2/1〜3/15。相続税申告は10か月以内。
評価の軸(混同注意):相続税・贈与税の評価は相続税評価(路線価/倍率方式)が軸。一方、登記や不動産取得税の課税標準は固定資産税評価額です。税目によって使う評価額が異なるため、試算時は必ず用途を切り分けます。
新ルール:暦年贈与の「7年加算」を正しく理解する
2024年以降の暦年贈与は、相続時に原則7年分を持ち戻して課税価格に加算します。
・段階的適用:死亡時期により加算対象が広がる経過措置があり、従来の3年→(段階拡大)→最終的に7年へ移行します。
・100万円控除の位置づけ:4〜7年前に行った贈与の加算は「各年ごと」ではなく「合計額から100万円を控除した残額」で行います。このため、各年110万円以下の贈与でも、合計が100万円を超えれば加算され得ます。
・結果として、安易な「毎年110万円」の暦年贈与だけでは節税にならない場面が増加。生前贈与は、目的(地価・トラブル・資金需要)を明確化し、相続時精算課税などと選択・併用して設計する必要があります。
税金のシミュレーション:具体例で見る(数字で比較)
前提:評価は概算。相続税評価(路線価)と固定資産税評価は異なるため、登記・取得税の計算は固定資産税評価額で行います。相続人構成・債務・預貯金・生命保険などで結果は変動します。
ケース1|評価2,000万円の自宅土地(相続人:子1人)
A. 生前贈与(暦年課税・一括)… 贈与税(特例):(2,000−110)×45%−265=約585.5万円。登記2.0%:1,400×2%=28万円。取得税:1,400×1/2×3%=21万円。→合計約635万円。
B. 相続 … 基礎控除3,600万円>2,000万円→相続税0円(さらに小規模宅地等で圧縮余地)。登記0.4%:1,400×0.4%=5.6万円。取得税:非課税。→合計約5.6万円。
結論:この前提なら相続が圧倒的に有利(差約629万円)。
ケース2|評価5,000万円の土地(相続人:子2人・配偶者なし)
A. 生前贈与(暦年課税・一括)… 贈与税(特例):(5,000−110)×55%−640=約2,049.5万円。登記2.0%:3,500×2%=70万円。取得税:3,500×1/2×3%=52.5万円。→合計約2,172万円。
B-1. 相続(特例なし)… 課税価格超過:5,000−(3,000+600×2)=800万円。法定相続分で各400万円→税率10%→合計約80万円。登記0.4%:3,500×0.4%=14万円。→合計約94万円。
B-2. 相続(自宅・小規模宅地等の特例あり)… 居住330㎡内80%減で評価大幅圧縮→相続税0円も十分あり得る。
結論:相続>贈与。特に自宅敷地で特例適用なら差は決定的。贈与が有利になるのは、自宅以外で評価上昇が濃厚かつ相続特例の恩恵が小さい土地に限られます。
生前贈与が有利なケース
① 相続トラブルを避けたい・共有を作りたくない
相続人が複数で利害も異なる場合、遺産分割協議は時間がかかり、結果として共有持分のまま放置されると売却・建替え・賃貸などの意思決定が難航します。生前贈与で受け手・持分・負担(固定資産税・修繕等)を明確化しておけば、相続開始後の争点を事前に消すことが可能。将来の空き家・空き地化リスクを抑制できます。
② 早期に資産を活用したい(売却・建替え・資金化)
贈与後は受贈者名義で即時に資産活用へ移行できます。さらに住宅取得等資金の非課税(省エネ等住宅1,000万円/一般500万円)を活用すれば、資金移転しながら家族全体の住まい計画を前倒しできます(要件多数/贈与年は令和6〜8年(2024〜2026)が目安)。
③ 将来的な地価上昇が見込まれる土地
新駅・再開発・沿線魅力度の向上などで評価上昇が見込まれる土地は、相続時精算課税を活用して現時点の評価で移転し、贈与時負担を抑えつつ受贈者世代での活用・再投資の主導権を早める設計が考えられます(最終は相続時に清算)。一方で、7年加算や将来の納税資金確保を同時に設計することが必須です。
相続が有利なケース
① 相続財産が基礎控除内に収まる
基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)内であれば、相続税は非課税。諸税コスト(登記0.4%/取得税非課税)も相続が圧倒的に軽いため、特段の事情がなければ相続>贈与が定石です。
② 小規模宅地等の特例など「相続特例」を使える
居住用(330㎡・80%減)、事業用、貸付用など対象や限度が明確な特例は、適用要件を満たせば相続税を大幅に圧縮できます。特に自宅敷地の承継では相続を前提に遺言・同居・持戻しの有無などをセットで整えるのが王道です。
手続きの簡便さを比較する(贈与・相続の実務フロー)
生前贈与の流れ
1)贈与契約書の作成(当事者・対象不動産・持分・負担付の有無・時期等/公正証書化を推奨)。
2)登記(司法書士手配。課税標準は固定資産税評価額。登録免許税2.0%)。
3)贈与税申告(受贈者が翌年2/1〜3/15に申告・納付)。
4)不動産取得税(県税:贈与は課税。住宅・宅地は3%、宅地は課税標準1/2の軽減。現行は令和9年3月31日までが目安)。
相続の流れ
1)遺言書の確認→相続人・財産の調査→遺産分割協議。
2)相続税評価(路線価・倍率)と申告要否の判定(必要なら10か月以内に申告・納付)。
3)相続登記(登録免許税0.4%。相続で取得したことを知った日から3年以内に申請義務)。
4)不動産取得税:相続は非課税(県税)。
生前贈与と相続の注意点
贈与契約書の重要性(「口約束」はNG)
贈与は合意で成立しますが、証拠化が不十分だと税務否認や家族間紛争の火種に。金額・物件特定・負担付・撤回条項などを明記し、登記・申告まで一体で完了させましょう。振込履歴や領収書の保存も有効です。
7年加算と相続時精算課税の設計
暦年贈与は相続時の加算を見据え、110万円枠だけでなく4〜7年合計−100万円の加算ルールを理解したうえで配分・タイミングを決めます。相続時精算課税は年110万円の基礎控除が使えるようになりましたが、同一贈与者について原則制度を戻せないため、初回からゴール設定が必須です。
特例の適用可否(重ね掛けは不可のものも)
小規模宅地等の特例は相続に限定、贈与では使えません。住宅取得等資金の非課税は面積・性能・契約時期・贈与年など要件が厳格です。配偶者への居住用贈与(いわゆる「おしどり贈与」)は2,000万円+110万円の枠が魅力ですが、相続の配偶者控除・小規模宅地との総合最適を比較しましょう。
専門家に相談するメリット(税理士・司法書士の役割)
税理士:相続税評価(路線価・倍率・補正)と特例適用可否の精査、贈与税・相続税の試算、申告実務まで一気通貫。7年加算や相続時精算課税(年110万円)を踏まえた最適ルート設計に強み。
司法書士:贈与・相続の登記実務(必要書類の収集・作成、登録免許税の試算)、相続登記3年義務化を踏まえたスケジュール管理。
当店(ハウスドゥ取手戸頭店):取手市・利根町の相場・路線価の肌感と売却・賃貸の実務を統合。査定→活用設計→売却・賃貸→税・登記連携までワンストップで伴走します。

店長:石塚 正美(いしづか まさみ)/初回相談は無料。評価の考え方・特例の適用可否・諸税コストを1枚の試算表に落とし込み、最短ルートをご提案します。
まとめ:どちらが得かはケースバイケース
判断の手順(推奨)
1)資産棚卸し(相続税評価の概算・債務含む)→ 2)基礎控除内か?・自宅特例が効くか?を判定 → 3)重い場合は贈与の狙いどころ(地価上昇、トラブル回避、資金需要)を明確化 → 4)7年加算・年110万円・2,500万円・10か月・3年を逆算して具体策に落とす。
具体的な行動:相続案/贈与案の2本試算を並走→家族の意向(居住・売却・共有回避・事業承継)を文書化→当店+税理士+司法書士で一体検討し、実行計画へ。
FAQ(よくある質問)
Q1:固定資産税評価額と路線価、どちらを見ればいい?
A:贈与税・相続税は路線価(相続税評価)、登記・不動産取得税は固定資産税評価額が軸です。税目で使う評価額が違うのが最大の落とし穴。迷ったら用途→評価額の順で確認を。
Q2:暦年贈与の110万円は、もう安全ではない?
A:2024年以降は原則7年加算で、4〜7年前分は合計から100万円控除後の残額を加算します。各年110万円以下でも合計次第で加算されるため、目的別の制度選択・タイミング設計が重要です。
Q3:相続時精算課税は結局お得?
A:贈与時は2,500万円+年110万円まで贈与税の負担を抑えつつ前倒し承継できますが、最終的に相続時に清算。地価上昇・トラブル回避・資金需要など明確な目的がある時に力を発揮します。
Q4:配偶者に家を贈与すると2,000万円まで非課税って本当?
A:婚姻20年以上の配偶者への居住用不動産(または取得資金)の贈与では、2,000万円+110万円の控除が使えます(いわゆる「おしどり贈与」)。ただし、相続の配偶者控除・小規模宅地との比較で総合最適を。
Q5:相続の申告・登記の期限は?
A:相続税は10か月、相続登記は3年以内に申請義務。贈与税は翌年3/15まで。期限逆算で準備しましょう。
Q6:贈与と相続、どちらでも不動産取得税はかかる?
A:贈与は課税(住宅・宅地は特例で3%、宅地1/2の軽減あり/期限・要件に注意)、相続は非課税です。取手・利根エリアは茨城県の運用に従います。
Q7:全部任せたい
A:当店が査定→活用設計→売却・賃貸→税・登記連携までをワンストップで伴走します。初回相談は無料、秘密厳守で対応します。
※本記事は2025年11月時点の公表情報に基づき作成しています。税制・特例の適用は要件・期限に左右されます。個別事情(同居・生計・事業・貸付・負担付贈与など)で結果が大きく変わるため、最終判断は税理士・司法書士などの専門家へご確認ください。